オンラインイベント
(木)~
第2回 The New England Journal of Medicine 論文著者に聞く NEJMへの投稿・掲載のリアル
南江堂によるオンラインイベント「The New England Journal of Medicine 論文著者に聞く NEJMへの投稿・掲載のリアル」では、NEJMに論文が掲載された医師や研究者をお招きし、投稿から掲載の過程や、その後の反響などをお聞きします。
第2回目となる今回は、2020年に論文がNEJMに掲載された椛島 健治先生と、モデレーターとして大塚 篤司先生にご登壇いただきました。
- 講演者
-
- 椛島 健治 氏

- 京都大学大学院
医学研究科
皮膚科学教授
- モデレーター
-
- 大塚 篤司 氏

- 近畿大学医学部
皮膚科学教室
主任教授
講演:かゆみを標的にしたアトピー性皮膚炎の新たな治療戦略 ― IL-31受容体の中和抗体によるアトピー性皮膚炎のかゆみと症状の緩和
アトピー性皮膚炎の三位一体論

世界にはアトピー性皮膚炎の患者が2億人以上、日本国内にも数十万から数百万人いると言われています。この病気の本態は湿疹ができやすい体質とされますが、いろんな側面のある複雑な疾患で、さまざまな要因があると考えられます。
病態を整理して考えていくうちに、アトピー性皮膚炎というのは、皮膚のバリアと、今で言う2型炎症と、かゆみ(そう痒)という3つの要素が三位一体となって病態に関係しているのではないかというアイディアに至りました。簡単に説明すると、フィラグリンなどの遺伝的な素因や石鹸などの使いすぎでバリアが壊れる。その中で抗原への曝露によって2型炎症が誘発されてIgEが上昇すると、アトピー性皮膚炎や他臓器のアレルギーにつながる。2型炎症が産生するさまざまなサイトカインがかゆみを誘導し、掻けばバリアが壊れる。このようにバリア、2型炎症、かゆみの3つの要素があるのではないかと考えたわけです。この内容は2013年にJournal of Dermatological Scienceで発表しています。
治療の側面からこの3つの要素を見ると、炎症に対しては、ステロイドの外用剤やタクロリムス軟膏という十分な薬があります。ところが、かゆみに対して使われる抗ヒスタミン薬はなかなか効かない。また、バリアには保湿剤がありますが、壊れたバリアの上に薄い油の膜を塗るだけではなかなか歯が立たない。さらに、ステロイドを塗るとバリア機能は脆弱になります。そこで、これからの治療法を開発するには、バリアとかゆみに対象を絞っていくのがいいのではないかと考えるようになりました。
創薬研究の開始とバリアへの注目
2008年に京都大学のAKプロジェクト(次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点)で独立准教授となり、製薬会社と共同で、初めて創薬を意識して研究をすることになりました。今日のモデレーターである大塚先生とはそのときから一緒に仕事をしています。
そこではまずバリアのほうに注目しました。つまり、バリアさえ壊れなければアレルゲンは皮膚の中に侵入できない、そうすれば自然とアトピーは治るはずだと。実際にやったのは、ヒトの皮膚の細胞を培養して、化学ライブラリーの中からフィラグリンの発現やバリア機能を亢進させる化合物を同定していくということでした。言葉では簡単ですが、非常に辛気臭く、大変な労力の要ることです。このなかで、大塚先生が見出したJTC801はフィラグリンを亢進させ、マウスにおいて皮膚の炎症を予防することがわかりました。また、ほぼ同時期にJAK阻害薬にも注目し、去年発売になったデルゴシチニブ(商品名:コレクチム軟膏)の開発に至りました。これはバリア機能を高めつつ炎症も抑える薬で、ステロイド以外の治療薬ができたことはよかったと思っています。
かゆみへの注目
さて、もう一つの問題はかゆみです。アトピー性皮膚炎の患者さんの一番の苦しみは、かゆみによって眠りが浅くなるなどQOLが低下することです。また、あまり掻けない場所は湿疹がそれほどひどくならないことを臨床上よく経験しています。搔かなければアトピーがよくなるのではないか。すなわち、掻くことを抑える薬を開発すればいいのではないかと考えるようになりました。
ところが、かゆみのメディエータは非常にたくさんあります。肥満細胞由来のヒスタミン、プロスタグランジン、神経由来のサブスタンスP、透析に伴うかゆみではエンケファリン、モルヒネ様物質も挙げられます。臨床の現場でよく使われている抗ヒスタミン薬は、じんましんのかゆみには効くのですが、アトピーにはあまり効かないことから、アトピーのかゆみはそれ以外のメディエータだろうということが推測されるわけです。
一方で、アトピーの重症の患者さんに免疫抑制剤のシクロスポリン内服薬を用いると、皮疹が良くなっていない段階でも、かゆみがスッとおさまることがあります。そこで、もしかするとT細胞がかゆみを誘導しているのかもしれないという仮説が立てられるわけです。
2004年に、海外のグループから非常に興味深い論文が出ました。IL-31をマウスの皮膚に注射すると、アトピー様の皮膚炎、湿疹を誘導するという報告です。さらにその後の研究により、IL-31はT細胞が産生し、アトピーの患者さんではIL-31が上昇していることがわかってきました。このことから、T細胞がIL-31を出し、IL-31受容体に作用してかゆみを誘導するという仮説が立てられます。我々は、マウスだけではなくヒトでもそうなのかということに注目し、シクロスポリンを投与するとかゆみが抑えられると同時にIL-31が低下することを見出しました。
2010年に、Conference for BioSignal and Medicine(CBSM)という、松田浩珍先生(東京農工大学<当時>)や田中啓二先生(東京都臨床医学総合研究所<当時>)ら、基礎の先生方が開催した研究会にたまたま呼んでいただき、アトピーの話をしました。そこで中外製薬の方が、「アトピーにおもしろそうなのがあるんですよ」と話しかけてくださり、IL-31に非常に興味を持っていることがわかりました。中外製薬はIL-6中和抗体のアクテムラで成功して、次のターゲットの一つがこのIL-31だったのです。彼らは、IL-31の受容体をブロックする中和抗体をつくればどうだろうかと考えていました。ネモリズマブとなる抗体です。この出会いから、今回の研究が始まりました。当時はIL-31以外にも多くの候補があるなかで、これからはかゆみを抑えることが重要になるという考えから、かゆみを抑えるこの抗体をちゃんと世に出せるかどうかを検証するところで自分が貢献したい、この治療薬に全面的に貢献していこう、と決心しました。
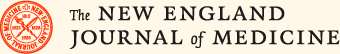

2020年にThe New England Journal of Medicineに掲載された論文「瘙痒を伴うアトピー性皮膚炎に対するネモリズマブと外用薬の試験」について、僕がアトピー性皮膚炎の治療薬の開発に向かっていった経緯からお話しさせていただきます。
僕は学生のときに免疫やアレルギーに興味を持ち、免疫グロブリンE(IgE)を発見された石坂公成先生のお弟子さんである淀井淳司先生の教室で研究させてもらいました。その後、アメリカ国立衛生研究所(NIH)に留学したことがきっかけで、臨床と研究の両方をやれる仕事を目指すようになりました。
皮膚科に入ってからは、アトピー性皮膚炎に関心をもちました。入局した頃はいわゆるアトピービジネスが蔓延していて、ステロイド外用剤を全く使わずひどい状態の皮膚になって外来に来る患者さんを診察しながら、なんとか良い治療薬がつくれないかという思いで臨床と研究に臨んでいました。