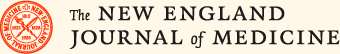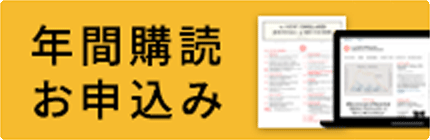![]()
Escherichia coli(大腸菌)O157:H7 感染症の抗生剤治療後における溶血性尿毒症症候群のリスク
The Risk of the Hemolytic–Uremic Syndrome after Antibiotic Treatment of Escherichia coli O157:H7 Infections
C.S. WONG, S. JELACIC, R.L. HABEEB, S.L. WATKINS, AND P.I. TARR
Escherichia coli(大腸菌)O157:H7 による消化管感染症を起こした小児は,溶血性尿毒症症候群を発症するリスクがある.しかし,このリスクが抗生剤の使用によって変化するのかどうかということはわかっていない.
Escherichia coli O157:H7 による下痢を発症した 10 歳未満の小児 71 例を対象とした前向きコホート研究を実施し,これらの小児への抗生剤治療が溶血性尿毒症症候群のリスクに影響を及ぼすのかどうかを評価するとともに,交絡因子がこの転帰に及ぼしている影響についても評価した.相対リスクの推定値には,ロジスティック回帰分析を用いて可能性のある交絡の影響を補正した.
71 例のうち,9 例(13%)に抗生剤の投与が行われ,10 例(14%)が溶血性尿毒症症候群を発症した.溶血性尿毒症症候群を発症した 10 例のうち,5 例に抗生剤の投与が行われていた.溶血性尿毒症症候群との有意な関連が認められた因子は,初回検査での白血球数増加(相対リスク,1.3;95%信頼区間,1.1~1.5),発症後早期の便培養の評価(相対リスク,0.3;95%信頼区間,0.2~0.8),および抗生剤治療(相対リスク,14.3;95%信頼区間,2.9~70.7)であった.抗生剤の投与を受けた 9 例の臨床特性と臨床検査特性は,抗生剤の投与を受けなかった 62 例の特性と類似していた.初回検査の白血球数および培養用糞便の採取病日によって補正した多変量解析でも,抗生剤の投与は溶血性尿毒症症候群発症の危険因子であった(相対リスク,17.3;95%信頼区間,2.2~137).
E. coli O157:H7 感染症の小児に対する抗生剤治療は,溶血性尿毒症症候群のリスクを上昇させる.